![]()
北原 隆志 先生
山口大学医学部附属病院 薬剤部長
![]()
豊福さん
ファイザーの新入社員。最近はまっていることは「レッサーパンダの動画を見る」こと。
![]()
須永さん
ファイザーの新入社員。趣味はボディビル。
感染症はウイルスだけではなく、細菌などさまざまな病原体によって引き起こされます。この病原体に薬が効かなくなる「薬剤耐性(AMR:エイエムアール)」が問題になっており、私たちの生活に大きな影響を与える懸念があります。
そのAMRとは一体何なのか、なぜ問題になっているのか、どのように対策すれば良いのかを、全4回にわたって、専門家の方々にファイザーの新入社員が聞いていきます。
今回は「抗菌薬って何だろう」をテーマに、薬の専門家の薬剤師である北原 隆志 先生にお話を伺いました。今回のお話では抗菌薬の実情やAMR対策における薬剤師さんの役割が見えてきました。
![]()
北原 隆志 先生
山口大学医学部附属病院 薬剤部長
![]()
豊福さん
ファイザーの新入社員。最近はまっていることは「レッサーパンダの動画を見る」こと。
![]()
須永さん
ファイザーの新入社員。趣味はボディビル。
INTERVIEW INDEX
1.薬剤師ってどういうお仕事?
2.薬剤師が行っているAMR対策
3.薬剤耐性菌の現状
4.自己判断で抗菌薬を扱うことは危険
![]()
![]()
先生、今日はよろしくお願いします。
![]()
よろしくお願いします。
まず「薬剤師」と聞いて、どのような姿をイメージしますか?
![]()
薬局にいる薬剤師さんの姿が浮かびます。
私たちが服用する薬を調剤してくれているイメージですが、その他にも役割があるのでしょうか。
![]()
実は薬局以外にも、病院や診療所で多くの薬剤師さんが働いています。
医療現場では医師や看護師、検査技師、薬剤師など、さまざまな職種の方がチームを組んで治療にあたっています。この「チーム医療」が、良質な医療を実現するためには不可欠で、医療の質はこのチームがうまく機能しているかどうかにかかっていると言っても良いくらいです。こうしたチーム医療のなかで薬剤師は薬のプロとして、調剤以外にも大切な役割を担っています。
薬には症状を和らげたり病原体をやっつけたりする「効果」があると同時に、有害な作用である「副作用」があります。薬の効果を最大限に活かし、副作用を最小限に抑えることは薬剤師の責務ですので、処方する薬の量や種類を医師に助言することもあります。
![]()
同じ患者さんに対して、お医者さんと薬剤師さんでは視点が違うのでしょうか?
![]()
基本見方は違いますね。
医師が、患者さんの症状の観点から薬を処方するのに対して、薬剤師は、その処方に対して患者さんに副作用の兆候がないか、他の薬との相互作用はどうかなど薬の観点から見ます。
私は薬理学を「医学部」の学生に講義していますが、「薬学部」の学生に教えることと内容やポイントに違いがあります。

![]()
視点が異なるのであれば、現場で意見が食い違うということもありますか?
![]()
そういうことはありますが、良い方向になるように双方が議論することは良いことですよね。最近の医師は、薬剤師の意見も非常に真剣に聴いてくれますよ。
![]()
AMR対策にも薬剤師さんは関わっているのでしょうか?
![]()
山口大学医学部附属病院のAMR対策では「抗菌薬適正使用支援チーム」(AST:Antimicrobial Stewardship Team)というチームが中心になっています。ここに薬剤師、医師、看護師などがいて、各病棟、病室で抗菌薬が適正に使用されているかどうかをさまざまな角度からチェックします。ASTは、以前は一部の病院が独自に立ち上げていたのですが、2018年には診療報酬の対象になったことで全国に広がっています。
![]()
抗菌薬が適正に使用されているかどうかは、どのようにチェックするのでしょうか。
![]()
山口大学医学部附属病院では感染症の発生状況の定期的なチェックに加え、各病棟、病室ごとにどのような抗菌薬の使われ方をしているかをモニターしています。用法用量は適切か、投与期間が長すぎないか、患者さんから問題となる菌が検出されなくなったのに薬が使われ続けていないかなどをチェックします。また広域スペクトラムを有するいくつかの抗菌薬を使用する場合は事前にASTに申請してもらうようにしています。もし適正でない使われ方をしている懸念があれば、主治医と相談する体制をとっています。
![]()
広域スペクトラムを有する抗菌薬とはどのようなものでしょうか?

![]()
抗菌薬は特定の細菌に対して使用しますが、幅広い種類の細菌に効く=広域スペクトラムを有する抗菌薬も存在しており、これを「広域抗菌薬」といいます。広域抗菌薬は便利な薬ですが、過剰な使用は患者さんの体内の薬剤耐性のない細菌をやっつけてしまい、薬剤耐性菌のみが生き残る環境をつくりだしてしまいます。これはその他の抗菌薬でも起こりうることですが、広域抗菌薬ではその懸念がさらに高まります。
![]()
たくさんの種類の細菌に効く抗菌薬だからといって、安易に使用するとAMRを起こしてしまうのですね。
![]()
その通りです。
そして抗菌薬の適正使用は医療関係者が努力するだけでは達成されませんので、患者さんやそのご家族の皆さんにも、抗菌薬の特徴や使用する目的を理解していただくことが必要なのです。
たとえば風邪はウイルスが原因ですから、細菌をやっつけるために作られた抗菌薬は効きません。しかし風邪で病院を受診して抗菌薬が出ないと、「あの先生は薬も出してくれなかった」と不満に思う患者さんも少なくありません。医師の一部には効果がないことがわかっていても、患者さんから「薬を出してください」とお願いされれば処方する医師もいます。結果、日本では風邪に対して多くの抗菌薬が処方され、そのことがAMRを助長する一因になってしまいました。
![]()
わたしたち一般市民が抗菌薬についてしっかりと理解すれば、不必要な抗菌薬を求めることもありませんね。
でも、抗菌薬で風邪がよくなったという話も聞いたことがあります。
![]()
それは抗菌薬が効いたということではないのですよ。
多くの風邪は免疫が正常であれば1週間程度で治りますし、おそらく抗菌薬だけでなく、他の症状を抑える薬も処方され、服用していると思います。しかし治る前にたまたま抗菌薬を服用していたので、抗菌薬のおかげで治ったと錯覚してしまいがちなのです。
実は処方される抗菌薬のうち90%は内服薬(飲み薬)で、適正使用の大きな課題となっています。つまり、飲み忘れや、治ったという自己判断による服用の中止が起きがちだということです。そのため、こうして皆さんに抗菌薬の正しい使い方について知ってもらう機会を多くつくるようにしています。
そして抗菌薬の不必要な使用を減らすことも必要です。政府のAMR対策アクションプランでは、医療で使用される抗菌薬の使用量を2013年に比べ、2020年では33%減らすことを目標に掲げました。まだ達成されていませんが、年々抗菌薬の使用量は減少しています。
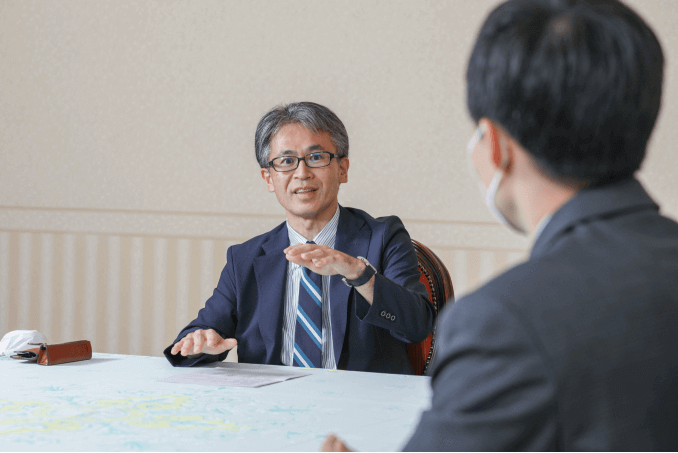
![]()
医療関係者の方々と私たち一般市民の努力で、AMRに立ち向かっていかなければならないことがよくわかりました。
![]()
どの程度の細菌が薬剤に耐性をもっているのでしょうか。
![]()
病気や細菌の種類によって異なるので一概には言えませんが、2014年の調査では、医療分野で検出される肺炎球菌の48%がペニシリンという薬の耐性、黄色ブドウ球菌の51%がメチシリンの耐性、緑膿菌の17%がカルバペネムの耐性をもっています。
![]()
薬剤耐性菌はそんなに多くの割合を占めてしまっているのですね。
現在、医療現場で問題になっている菌にはどのようなものがありますか?

![]()
まずMRSA(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)です。これはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の略ですが、どの医療機関でも最も多く検出される薬剤耐性菌です。日本のAMR対策アクションプランでは、2014年時点での耐性化率51%を2020年に20%以下にしようという目標を掲げたのですが、達成できていません。
ESBL(Extended Spectrum βLactamase)産生菌も問題になっています。抗菌薬の1つであるペニシリン系薬を分解してしまう酵素(クラスA β-ラクタマーゼ)があるのですが、この酵素がペニシリン系薬だけでなくセファロスポリン系薬までも分解してしまうようになったものです。細菌感染症に広く使われてきた薬が効かなくなるため、対処に注意が必要な薬剤耐性菌です。
カルバペネム耐性緑膿菌も注意が必要です。さまざまな薬剤耐性菌をやっつけるための「最後の切り札」として使用されてきたカルバペネムという抗菌薬が効かない薬剤耐性菌ですので、感染してしまうと治療が非常に困難です。
![]()
最後に一般の方に伝えたいことはありますか?
![]()
他の先生方も仰ってきたと思いますが、どのような薬をどのような用量でいつまで飲むのかを確認し、処方された薬は最後まで飲んでください。副作用が心配になったり、実際に出た時は、医師や薬剤師に相談してください。
よく“飲み残した薬”を保管しておいて、家族が病気になった時にあげる方がいますが、大変危険ですので絶対にやめましょう。もらった抗菌薬で重い副作用が起こることもありますし、風邪のような症状でも実は別の病気であることもあります。自分に処方された薬を乳幼児に与える保護者の方もいらっしゃいますが、そもそも成人と乳幼児では薬の用量が違いますし、乳幼児は薬の副作用による不調を訴えることができず、後遺症が残ってしまったという事例もあります。
抗菌薬は身近な薬ですが、専門知識がない方が気軽に使うことができる薬ではありません。自己判断で使用することはせずに、医師や薬剤師の指示に従って正しく使ってほしいと思います。
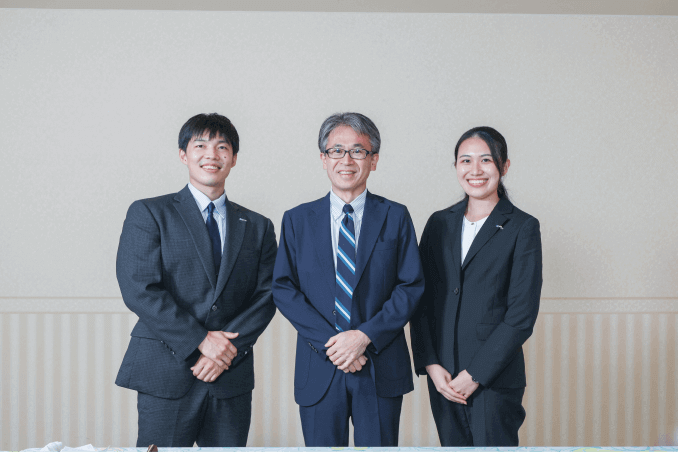
今回のポイント
① 薬剤耐性菌にもさまざまな種類があり、その問題は深刻化しています。
② 薬剤師は“薬のプロフェッショナル”として、AMR対策にも取り組んでいます。
③ 私たち一般市民も抗菌薬の正しい使用でAMR対策に取り組みましょう。
※掲載されている本文と写真は取材当時(2022年11月)のものです